Book Archive
今の日本のホームレス。『地上の人々―三人のホームレス 』(パロル舎刊)を読む
パロル舎刊の『地上の人々―三人のホームレス』を読む。
図書新聞の井手さんが一人称で、水道橋界隈の三人のホームレスをルポした作品。私小説のようでもある。
3人は、若い時分から身体を資本に働き、怪我や老年、勤め先の倒産などをきっかけにホームレスに行き着く。
「昔は、50歳くらいまで働けたら良かった。それが寿命が伸びて、60代までは頑張ろうと思っていたら、今や80代まで生きれるようになってしまった」というようなセリフにあるように、「人間、働けなくなってからの人生が長い」というのを考えさせられます。
一方で、なんだかんだたくましく生きる(ように見えただけかもしれませんが)彼らの姿に、人間は意外にも強いのか?とも……。
不況や格差なんて言われている世の中では、自分の将来に不安を感じる人も少なくないと思いますが、そういう意味では、人間なんだかんだで生きていけるという点においてはある種の希望を得られるかもしれません。
今の日本の陰の一面――「今の日本のホームレス」をそれ以上でもそれ以下でもなく、等身大にかいま見ることができる作品です。
パロル舎というと、絵本や芸術系に強い出版社というイメージですが、こういう味のあるテイストのドキュメンタリーを出すんですね。
『<弱さ>のちから』(著:鷲田清一)

鷲田清一の「弱さの力」を読みました。
ケアをテーマに、様々な場面にいる13人にインタビューし、著者の視点を交えながら記録した本でした。
臨床哲学という分野の(開拓した?)先生ということで、まさに、臨床の場(僕たちにとっては、日常生活の空間と言うべきかも)で起こる様々な現象——それも僕たちがあまり直視しようとしない現実——。それと正面から向き合っている人たちに話を聞いています。
例えば、住職、いじめ問題に取り組む先生、家族のあり方を模索する建築家、性感マッサージ嬢、24時間介護を必要とする元教師、など。
このインタビューを通して見えてくるのは、自分たちは実はとても脆い存在であるということ、弱さを抱えているということ。
さらにいえば、その弱さを、直視しないで過ごしていること。
例えば、24時間介護を必要とする元教師のエピソードですが、介護を必要とするその人のそばには、毎日誰かしらがいるそうです。時給650円程度で誰かが誰かを連れてきて、誰かしらが居る。日々の介護は介護をする側の人間にしても大変なことであり、時に自分にその役割が任せられて居ることに腹正しくなることもあるかもしれません。でも、この介護に関わる人が、その人によって救われていると感じる場面があるのです。
介護者が自分の日常の中では、笑ってごまかしている悩みや苦しみを、その人になら打ち明けることができるそうです。
「弱さは強さの欠如ではない」と著者は書きます。
日常を生きる我々は強くあることを推奨されるのか、自分の弱さに目を向けることを避けようとします。(まぁ、自分の弱さを声高に叫ぶ人もいるわけですが……。)
だから、相手のむき出しの弱さに触れた時、最初は戸惑うのです。それはきっと、直視することを避けて来た自分の弱さを直面することでもあるからだと思うのです。でも、その弱さが、自分の強張った身体をほぐし、自分にもある弱さを引き出してくれるのです。
日常を懸命に生きている私たちには、自分の弱さに目を向けられるような機会が必要です。
でも、自分を振り返ると、大学を出て社会に出て、仕事をして行く中で、自分の感情を無味にしてきた気がします。それは、自分をすり減らさないようにしてくれる一方で、無感動にもした気がします。
本の帯にも書かれてある「『そこに居てくれること』で、救われるのはだれか?」……。それは多分僕で、それは多分今を生きる私たち一人ひとりなのだと思います。
自分の弱さにも目を向けて、時にはそれを受け入れること……。それを思わせてくれる本でした。肩ひじを張って、張りつめて日常と向かっている人、でもその生活の一抹の不安を感じた時は読んでみると良いと思います。
……前職では、看護の方を取材することが多かったのですが、看護は、相手の弱さを受け入れ、そして、そこに居てくれる尊い仕事なのだな、と改めて感じました。
心病める人たち―開かれた精神医療へ (岩波新書)
- 2010-08-27 (金)
- Book
最近、看護を勉強している友人?から薦められた本を読みました。
看護学校一年目の課題図書として推薦された本だったそうで、近々、取材である精神病院を訪れるということもあり読みました。
岩波書店
売り上げランキング: 67960

 精神障害を知る、最初の一冊
精神障害を知る、最初の一冊  「精神障害」に直面した人への最高のバイブル。
「精神障害」に直面した人への最高のバイブル。 精神医療の実態を鮮烈に描く
精神医療の実態を鮮烈に描く
最近読んだ新書の中ではずば抜けて良書だったように思います。
戦後から1990年頃までの日本の精神病院やその治療について、自ら精神病院を設立して治療に取り組んできた石川先生が、ご自身の体験談を交えながら書いてあります。
普通、ちょっと風邪を引いたぐらいでは入院することはありません。せいぜい通院して薬を処方してもらい、家で養生することになります。
そこで医者から「風邪だ大変だ!すぐうちに入院しなさい」なんて言われたら「えっ?」て思います。
ところで、戦後の日本では「精神病」に対して同様のことが行われていたと著者は指摘します。(※僕の解釈も多分に入っていますが・・・)
それまで社会の中で暮らしていた多くの精神障害者が半ば強制的に入院させられてしまいます。
これは世間の偏見などももちろんあったでしょうが、
「国が奨励」→「民間の精神病院が乱立」→「(儲かるので?)入院患者集めに奔走」→「場合によっては本来入院が必要ないレベルの人を入院させ、(退院させない方が医療報酬が払われ儲かるので)良くなった人もひたすら長期入院させ続ける」
という流れもあったのだろうと推測されます。
さらには、精神病院は病床あたりの医師や看護などの医療スタッフの数が少なくてよいという特例があり、少ない人数で大人数を見るわけですから、そこに治療という発想は薄れて、鉄格子がついた病室に押し込み、ひどいところでは暴力によって、患者を支配するというような悪徳病院もあったそうです。
こうなると世間から見た精神病への誤解もデフレスパイラルに陥ります。少人数の医療者で無理矢理多くの患者を「収容」させるために設けた「鉄格子」が、地域の人たちの「鉄格子に入れられるような人を隣に住まわせるのか!」という偏見を呼ぶという悪循環です。
人間「知らないこと」に対しては当然ながら不安を持つ訳ですが、世間と隔離されきた患者さんのことは、当然ながら世間側の私たちも知らないわけで、いっそう「思い込みや偏見」が一人歩きをしてしまうそうです。
しっかりと治療に励む病院が別の問題に直面します。
いわゆる病気にかかって病院に入院した人は、
「入院治療」→「良くなってきたら、社会に送り返し、社会生活を営みながら外来治療」→「回復して社会復帰」
という流れの中で入院治療を受けます。これは精神病においても当然そうあるべきです。しかし、精神病の場合「世間の偏見と差別」により、さらには国の設定する医療制度の方針にも影響を受け、「社会に送り返し、社会生活を営みながら外来治療」というプロセスに進むことが難しかったそうです。(今もそうかもしれない・・・)
当時の日本では、そういった「社会復帰させよう」という意識のある病院は、収入が激減してしまうため、良心的な医療行為と持続性がトレードオフになってしまうという根本的な問題を抱えています。これはより良い精神医療を目指す人たちの大きな足かせになっています。こういった医療の改善のためには、政治や国の政策と無関係でないということもすごく意識させられます。。。
この本は、旧来の精神病院のあり方に対してNOを突きつけて、精神医療に取り組んできた著者の気概にあふれています。とにもかくにも、この問題の「一人称」として自ら奔走してきた著者の声は、資料やデータの寄せ集めでは決してできないメッセージがあり、色々と考えさせられる良書です。
僕が手に取ったこの本は、2009年33刷の本で、1990年からの約20年間読まれ続けてきています。この20年間でまた精神医療の現在がどう変わったかもすごく興味のあるところです。
石川先生が挙げていた問題点や課題点は改善されているのでしょうか。
ゆるゆる調べてみようかと思います。
確定申告と経済の分かりやすい本を読んでみる・・・
仕事しないと・・・と思いつつ、土曜日ということでつい本を読んでしまいました。。。現実逃避というやつですね。そういうことありません?
カメラマンとしての仕事は全て会社からの請求として出しているので、そんなに関係があるという意識はなかったのですが、確定申告等について全く知識がどうかなと思い、下記本を読みました。
日本実業出版社
売り上げランキング: 372

 おもしろかったけど
おもしろかったけど フリーランスでなくても参考になる
フリーランスでなくても参考になる 税金払いたくない!って思ったときに
税金払いたくない!って思ったときに これは、わかりやすい。
これは、わかりやすい。 この本は役にたたない(笑)
この本は役にたたない(笑)テクニカルな本ではなく、あくまで「どうして確定申告をせなあかんの?」「どうしてこういう形式になっているの?」「白色と青色ってどう違って、どっちがいいの?」なんて割とファンダメンタルな疑問に、またに「フリーランスを代表して聞いてきて」くれている印象の本です。
これを読むと、主体が「個人」なだけで、あくまで「法人」と似た感じで「売り上げ-経費=所得(利益かな?)」と同じ構造として扱われているということが理解できました。まさに「あ〜そういうことなんですね」と「聞かぬは一生の恥」的な気づきがありました。
例えば、サラリーマンの「給与控除」などは「経費」の代わりとして、結構「手厚く」保護されていて、「所得」って給料額ではなくて、「給料」からもろもろの「控除(=経費?)」を引いた額なのだそうです。。。そう理解できると売り上げの伸びてきたフリーランスがどうして法人化するのかなんてことも自然と見えてきます。(文中に分かりやすく説明ありますけどね)。
別の本でサラリーマンの結構な高収入な人が所得0扱いで税金がかかっていないという下りがあったのですが(下記)、基礎控除で65万円、扶養で38万円×人数なんだそうな・・・(数字は記憶ですが・・・)。
税金の仕組みって知らないと損するんだね。。。
2時間くらいでさくっと読めるし、なーんも分からんという人は本代の1400円とかすぐに回収できるのではないでしょうか。
ところで、去年から今年は不況の関係で「会社外のアルバイトを認める」というところが増えていると思うから、そういう人向けにも案内したらいいのに。(・・・ってそれは違う本でやるべきか)
ネットで調べてみると「バイトをしていることが会社にばれないための確定申告の仕方」みたいなのばかりですね。(会社とは別にアルバイト分の確定申告をして、住民税の支払いを会社天引きではなく、自分自身でやるという方法みたいです)。
で、実は併せて読んだ本が下記です。
2000年収録とかの本なので制度的に変わっているだろう部分はあるのですが、経済音痴の自分なんかにはもってこいの本でした。
何が良いかって、身近なたとえから経済の話に結びつけてくれるので理解しやすいということにつきます。
日本経済新聞社
売り上げランキング: 2705

 竹中氏に偏見を持つことなく読むべし
竹中氏に偏見を持つことなく読むべし 竹中氏の説明能力&佐藤氏の本質を掴む能力が素晴らしい
竹中氏の説明能力&佐藤氏の本質を掴む能力が素晴らしい QA方式でとても読みやすい本
QA方式でとても読みやすい本 わかりやすい、かわいい♪
わかりやすい、かわいい♪ 頭の良い人がする会話だから、分かりやすい
頭の良い人がする会話だから、分かりやすいで、本の中の下りにもあったのですが(どっちかは忘れました。多分、経済の方。)、サラリーマンは給料から税金が自動的に引き落としになっているので、税金に対する意識が低いというものでした。。。
確定申告して納めてたらそりゃ自分のお金がどう使われているかって気になりますもんね。
そういえば、昨年末に高校のOB/OG会に出たときに、愛媛から人が来ていて(地方自治体の人だったのか?)「ふるさと納税」の案内をしてくれたのですが、説明が的を射ないというか「何これ?よ〜わからん」という雰囲気が流れていたのですが、最近の本を読んで気がついたのは、この納税方式って実は納税者が自分で税金(の一部)を納める場所を選べるということが結構大事なのではないかと・・・。
もちろんその税金は地方の財源になるので、「自分には還元されん」や「ふるさと定義が曖昧」なんて意見もあるそうですが、面白い試みだし、愛媛がベースの人が多いうちのOB/OG会でちゃんと説明できたらやってくれた人も多かったろうに。。。もったいない。と、今更気がつきました。
世の中に疎い自分をどうかと思いつつ。
『「R25」のつくりかた』を参考にして・・・…
- 2009-03-28 (土)
- Book | Free Paper
「100万部の雑誌? タダにしたから、100万人にウケるわけじゃないでしょ。一万部の雑誌を100冊出したほうがいいんじゃない」
(『「R25」のつくりかた (日経プレミアシリーズ)』の「第1章 少人数の組織で「業界常識」に立ち向かう」より抜粋)
R25の制作準備中に編集長の藤井さんが知り合いの名物編集者から上記のことを言われたそうです。
実は看護学生向けのフリーペーパー『ナースのたまご』の制作に関わっていまして、
その課程で色々と参考になりそうな資料を探していたりします。
それで今回目にとまったのが、
お付き合い(≒飲み)をしている出版社の人たちと話をしていると、
新書や文庫、単行本に関してですが、本がそれこそ売れず――、
一万部出たら小ヒット!なんていっているのが、現状のようです。
5000部刷って2500部売れたら損益分離ラインだとして、ではいかにその2500部を確保できる角度の尖った本――対象がしっかりと明確になっている――を作るか、ということに、
腐心しています。
----------------
制作費を3割以下に抑えるというのが割と常識らしいですが、
仮に、1000円の本を5000部作るとして、全体で500万円分。
500万円×0.3≒150万円――印刷費や制作費を150万円で抑える。
すると、1000円の本が6掛けで流通に載るとして、1冊あたり600円の売上になる。
150万円÷600円≒2500冊。
2500冊売れて初めて赤黒トントンということになるそうです。
なので、後はいかに2500冊以上売れることが担保できる本を作るかという感じのようです。
----------------
一冊の本が大ヒット!!
ということがなくなった時代ですので、編集側もセグメントをしっかりとした本をたくさんの種類を出す!ということになります。
そういうのが割と常識的になっている時代ですので、100万部という大部数雑誌を発行する!!というR25の目標は、実に「蛮勇」という風に写っても仕方が無かった!!わけですし、藤井さんもそれを承知の上でR25の制作の臨んだそうです。
【Book Review】『文字講座』
ほんの数ヶ月前までフォントの違いに対して、無頓着でした。それが、今、なぜか「文字」に対して静かなるマイブームが起きています。
というのも今、簡単な文字組版をすることがあるのですが、その際、いつも文字周りでうんうん唸ることが多く、模索し、迷走します。
僕は何かをやるときに何かしらの基準軸を設けて、それを振りながら仮説立てし、実行して、反省、修正を加えるというプロセスを経るのが好ましいと思っているのですが、いかんせんフォントに関しては全く持ってどうしようもない状態が続いて来ました。
で、件の本。
そうそうたるアートディレクターのリレー講義を本にしたものみたいで、制作現場からの生の声はもちろん、実際にフォントを作る立場の人たちからの声もとても参考になります。
最終的に、自分なりにこの本を読んで納得した結論は、「フォントはあくまで素材の一つである」。結局、表現したいコンセプトや用途が先にあり、フォントはそれを表現するためにふさわしいものを選ぶべき、ということです。
今までは色々な人が発する、「helveticaが」「新ゴが」「MSゴシックなんて」というような言葉を鵜呑みにしてきましたが、そんなもんじゃないんだなって、よくよく考えればごくごく当たり前の結論に達しました。
(まぁ、ウェブだとシステムフォントが大方採用されるから、フォントなんて、、、みたいに思っていたというのもありましたが。。。)
個人的にはフォントが作られて来た歴史的な背景や、その時代の制作者の思いやストーリーが結構に楽しめました。
そのフォントが出来てきた背景が分かれば、それを一つの基準に据える事ができるなぁということを考え、テンションがあがりました。都度都度色々、調べて行こうと思います。
そういえば全くもって蛇足的な話なのですが、
(別にすべてを検証しているわけではないですが)ここ数年前から講談社の文庫本に読み辛さを感じます。
読みやすいようにとフォントサイズを大きくしたのはまぁいいとして、周辺余白をきちんと取っていないので親指が文字にひっかかる、本文の文字が明朝体なのは良いとしてウエイト(太さ)が若干太くて、長く読むものとしては、目が疲れる・・・という気がします。
別の出版社で、新書を編集者がインデザインで作っているという話を聞きました。スピードとコストの問題なのでしょうが、同様の事が起こっているのかな。。。
もう少し可読性を挙げてほしいところです。
技術の発達は専門性を下げ、そしてそれは良い仕様書に基づけば、うまく作用すると思うのですが、逆も起こりうる、ということですよね。
誠文堂新光社
売り上げランキング: 77305

 デザイナー必見!あのクリエイターのからの文字のお話。
デザイナー必見!あのクリエイターのからの文字のお話。【Book Review】『佐藤可士和の超整理術』『1冊まるごと佐藤可士和。』
ちょっと今更、という気もしますが、文化庁のメディア芸術祭を見に国立新美術館に行った際、メディアショップで佐藤可士和さんの本を2冊買いました。
アートディクレターの整理術って、という気もしつつも購入。
読んでみると、物理的な整理にももちろん言及はされてありますが、
本質的にはクライアントのRFP(requirement for proposal)を明確にするためのディレクションポリシーや(そこまで具体的な言及ではない気がしますが)手法について書かれてます。
やはり一線で活躍する人は、決して表面的ではない、本質的なビジョン・コンセプトを突き詰め(情報収集、仮説立て、検証)るのだなぁと感心。
仕事をしていると、担当窓口になるクライアントの満足に応えたら「事済む」こともあるのですが、やはりそれこそ実に表面的であり、クライアントと喧嘩してでも、本来のファンダメンタルなクライアントニーズを汲み取る事が大事なんだなぁと改めて感じました。
結局、本質的を押さえるから、結果につながり、結果が出るから、次につながる。
言われてみれば「当たり前」なのですが、日々の仕事をルーティンにしてしまう終業ではそれはとても見落としがちで、佐藤可士和さんは、実に本質的なディレクターなんだと、感嘆します。
仕事している人にとっては、新しい発見というより、見えているものを見落としていた自分に気が付ける本なのではないかと。
あと、実に理系的というか、システム的な発想部分も好きです。
日本経済新聞出版社
定価: ¥ 1,575
阪急コミュニケーションズ
定価: ¥ 1,575
【BookReview】「写真の読み方」(名取洋之助著)
- 2009-02-04 (水)
- Book
「写真の読み方」というタイトルに惹かれたというより、著者、名取洋之助に惹かれて購入。
アンコール復刻ということで表紙も緑と、岩波新書でも珍しい色。
日本の写真界の草創期といえば、木村伊兵衛や土門拳が著名だが、
名取洋之助も同時期の人で、世界からすると名前が出たのは二人よりも早く、
ドイツ留学中に目覚めた写真でドイツのジャーナル誌でデビューし、
『ライフ』の専属カメラマンとしても活躍した。
帰国してからは『日本工房』という事務所を構え、木村伊兵衛、土門拳、三木淳など、今や名だたる日本の写真賞の冠になる人たちを巻き込んで写真を活動を行っていた。
(3~4年前に、名取洋之助賞が遅ればせながら創設されました)
実は、私は個人として名取洋之助の撮影スタイルに共感する部分が割りと強いのですが、
それは例えば、彼が「純粋な写真家」というよりは、写真というツールを武器にもった「企画屋」であり、「編集者」であり、「アートディレクター」であるという点。
写真と+α(ex.言葉、構成、デザイン... etc)を用いて訴求力を強めていくというスタンスを取るからです。
確かに「一枚の写真の訴求力」となった時、木村伊兵衛、土門拳、ロバートキャパの撮った写真ほどに心に染みいりはしないのですが、翻って、合わせ技で表現に伸びを出す、というのは、写真単独での表現に力不足を感じないわけにはいかず、色々な表現手段との合わせ技を考えないではいられない僕にとってはすごく(若輩者が厚かましい限りですが)共感する部分があります。
そして、写真を素材の1つとして捉え、総合的にどのように表現をしていくと人に訴求できるか――という観点で語られた名取洋之助の言葉は、とてもコンセプチュアルで、それゆえに、例えばITが発達してきた現在においても、色あせることないメッセージとして伝わってきます。
著者没後から46~47年経つそうですが。
今の時代に重ねて読んでも「そうだよね」と共感する部分も多いです。
戦前・戦後の日本の写真(産業)の歴史という観点でも勉強になります。
※ちなみに全く持って蛇足ですが、個人的に、
名取洋之助の「アートディレクター」的な志向に、反発して(日本工房時代はすごいこき使われていたという話ですし)、土門拳は「絶対リアリズム」という風に傾倒していったのではないかなーとも、想像しています。
「落語は人間の業の肯定である」
立川談春の『赤めだか』を読んだ。
近くの本屋で平積みされていたのに少し気になっていたところ、
時々、出稽古させていただいている上野先生(落語好き)に、
写真の世界を話いただいた際、「『赤めだか』という本があって、写真の世界もあれと同じだよ。」とお勧めいただいたこともあり、手に取った。
談春は、以前、一度聞いたことがあるんですが(以前のエントリー、立川談春の落語を聞いて来ました)、
『赤めだか』は、自叙伝というか、エッセーというか、な感じです。
カメラマンの仕事であるところの「撮影」も一種の「芸」と考えたときに、
とてもしっくり来ることが多い――。
「芸を盗めなんて言うが、あれはキャリアのできる人間でしかできない」
「初めは型をまねることから始めよ」
「型のできてないやつが芝居をすると型なしになる。型のできているやつがオリジナリティを出せば型破りになる」
「型を作るには稽古しかない」
「やるやつはやるなと言ってもやるし、やらないやつはやれと言ってもやらない」
…空手の型でも同じことを聞いたし、剣道でも「守破離」ってあるけど、
やはりどの世界でも「道」は長いってことだよね。
しかし、談春が、高校を辞めて親に勘当され、住み込みの新聞配達をしながら弟子になった際の、談志の言いようがなんとも面白い。
端的にまとめると「落語家として成功したら美談になる。よしんば失敗しても、いっぱいやっているときのグチのネタになる」というもの。決して、一所懸命やりなさいとは、言わず、人生は決して思い通りに行くわけではないが、どう転んでもそれほど悪いことばかりではないだろう、ということを言外に伝えているのだろう、とのこと。
そういえば、以前、カメラマンとしては面白い経歴だから、成功したら面白いぜ、と言われたことがある。確かに、面白いかもね(逆に「退路だろ」って言われもするけどさ)。
この世界でいうと亜流で生きている以上、使えるものは使わないとだし、やるなと言われてもやらないと生きていけないような気がする。
自分と照らし合わせてもよい具合に引き締めてくれる本だった。
「落語は人間の業の肯定である」(談志)。
僕も見たいな人間も肯定してくれるというのだから、落語をもっと聞いてみようかな。
最近読んだ中ではかなりヒットでした。
ちなみに志らくの落語をPodcastingで見つけたので初めて聞いてみた。。。
「落語に狂気を持ち込む」志らくも、面白かったけど、談春の方が好きだ。
梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。③
高度情報化社会の流れの中で、総表現社会になりつつあるということについて、
前回大変うんうん頷いたわけですが、
その部分以外で、ブログに関して、共感したのが次の部分。
「ブログは個にとっての大いなる知的成長の場」であるという内容。(164ページ位)
ブログ書いておきながらこんなこと言うのははばかられますが、
僕のもともとのスタンスは「ブログなんて書く人の気が知れない」でした。苦笑
というのも、「石」の99パーセントにどうしても目が言ってしまい、
ルサンチマン(≒鬱憤?)の排泄であり、決して表現などではない!と思っていたからです。
(最近はもっとゆる~い捉え方になってますけどね。
そもそもネット内の情報なんて検索して精査してアクセスするわけだから、
基本1%の情報にピンポイントでアクセスできるので、石情報に自分が惑わされることもない。
さらに情報精査しないでアクセスするブログ情報は、
例えば友人のものだったりするわけだから、
それは逆に瑣末な情報から執筆者の人となりを想定させる効果があり、
「石」情報も必ずしも「石」ではなくなってしまう。
で、まぁ、色々とわけあってブログを書き始めて、
しかもできる限り日々更新すると(誰に誓うでもないけど)決心し、
毎日書いてみると当然ながら「ネタ切れ!!」するわけで、
それでも、些細なことでもひねり出しながら書いていると不思議なもの。
以前は適当に読み流していた本なんかでも、「何かしらのネタはない!?」と
兎視眈々と情報収集しようという風に思考が傾いていって、
アウトプットするために以前よりも貪欲にインプットするようになりました。
そういう体験もあったので、
「個の知的成長の場」
という表現はなかなかしっくり来ました。
この投稿するのにも、一度読みきった本(=『ウェブ進化論』)
を再び開いてる位ですからね。笑
梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。②
- 2007-10-07 (日)
- Book | Memo | Review | about Photo
梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。②
この本の第4章の「ブログと総表現社会」でブログについて色々と書かれています。
ちなみに海外だとオピニヨン発信の場として使われるブログも、
日本だと日記的に使う人が大半を占めていて、それで当然のことながら
ブログ数やエントリーの数も多いけれども、玉石混交――。
しかし、以前であれば、プロフェッショナルである物書きにしか許されてなかった、
情報発信を皆が手軽にできるようになった。
その多くは「石」なわけだが、下手したら99%は「石」かもしれないが、
残りの1%の「玉」――それもネット以前の社会であれば、
そういう素質がありながら、
もしくは、自分の専門分野があり、執筆のために雑食のごとく分野勉強する俄か専門の職業ライターさんよりも
はるかに一家言ある方がネットを通じて情報発信できるわけです。
当然ながらそれは有益な情報であり、それが仮に1%あれば、
母体数がそもそも多いわけですから、大変な数の有益が情報が発信されることになります。
それは素晴らしいことですね。
・・・・・・
なんかこれって写真でも似たような感覚に陥ることがあるのですが、
それは例えば報道の写真です。
今や携帯カメラに(そこそこ)高性能なカメラがついて、日本人全カメラマン的な状態です。
現場にいち早く到達し、訴求力のある写真を撮影する、
プロの報道カメラマンの価値がもちろん損なわれるわけではありませんが、
本当の決定的な瞬間――それも世の中の所かしこで起こっている決定的な瞬間の場面に
決して数の多くないプロの報道カメラマンが、居合わせる可能性は決して高くありません。
(それが叶って決定的な瞬間を捉えると、ピュリッツァー賞を取ったりするわけですよね。
…ちょっと語弊がありますけど、今回はご容赦を!)
それが日本人が全員「カメラマン」なら、決定的な出来事が起こったときに、
それが――たとえ稚拙でも――記録される可能性は極めて高くなります。
(報道は「きれい」よりも何よりも「写っていること」が重要ですから)。
これはブログで総表現社会になっている構造と同じことが写真の報道(...映像もそうかな?)についても言えるよなーと思った次第です。
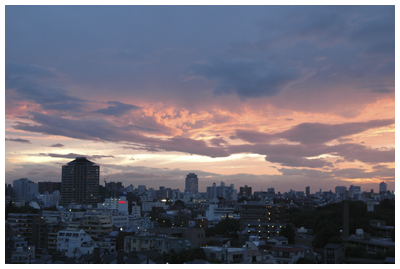
梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。
梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。
そうですよ。今更ですいませんね。
結論から言えば思ったよりも全然面白かった。
僕の知り合いの結構な人が持ってたし、
その人たちが結構にIT系の人たちだったなんてバイアスを差し引いても、
この本が結構なベストセラーだからなんですよね??
『ウェブ進化論』の読者としては、
僕は比較的にこの本を堪能できた部類の人間でしょう。
この中にはWEB2.0の話も割と出てくるのですが、
Googleを初めとするテクノロジー系の会社が提供する技術を享受して、
仕事をさせていただいているような立場の人間でもあるので(僕は)、
話題の大半を「他人事」ではなく「自分事」として捉えることができたということは大きいでしょう。
日常的なレベルの話で一例挙げるなら、
私は、会社のパソコン、家のパソコン、モバイルノートパソコンを
公私に渡って使っているのですが、
その際、いつも割りと困ってしまうのが、
例えば、作業しているファイルのバージョン管理や情報の集約先です。
ですので『ウェブ進化論』の言うところの「パソコンのあちら側」に、
ファイルやデータを集約させることで、ネットがつながる場所であれば、
どこからアクセスしても常に同様の環境で作業をすることができるので便利です。
もちろんネットが常に使えるわけでもないので、完璧に集約できているわけではないのですが、
情報収集においてのGoogeノート(最近使い初めました)やGmailは大変有益だな~としみじみ思います。
『冷血』(トルーマン・カポーティ)
トルーマン・カポーティの『冷血』を読み終わりました。
以前、カポーティという映画を見たのですが(以前のエントリー)、
その映画の中でフィリップシーモアホフマン演じるカポーティが
取材・執筆している作品が上記の、『冷血』でした。
1965年発表の作品です。
実際に起こった殺人事件を綿密に取材して、作品にしたというものです。
まず何よりも脱帽したのが、
文章一つ一つに膨大なデータの裏づけがあるだろうことが分かることです。
今でこそ、ノンフィクションジャンルは色々な作品がありますが、
(ちなみに沢木耕太郎の初期作品は大好きです)、
当時にしてみるとかなり真新しいものだったらしく、
以降、カポーティの縮小再生産のようなジャーナリズムが増えたそうですが…。
『冷血』を読んでみたらそれもなんとなく納得。
カポーティ本人がジャーナリズムというよりも、ノンフィクション・ノヴェルと本作品を位置づけているように、
ドキュメンタリーというよりもやはり「物語」です。
逆に、事実とその綿密な取材がベースであり、
最後のクライマックスと終焉を演出を「物語れる」からこそ
生み出せるリアリティ(≠真実)があるのでしょう。
そういった面において厳密には、ドキュメンタリーではないように思えますし、
それゆえ、カポーティに影響を受け、ドキュメンタリー作品に向かった記者が、
(綿密に取材するということは除いて)『冷血』に引きずられてしまえば、
陳腐なセンチメンタルに陥ってしまった作品が量産されてしまったことも不思議ではないかもしれません。
以後、死屍累々の作品を生み出す潮流となった一種の問題作は読む価値ありですよ。







